― 息苦しさと闘う患者さんのために、今できること ―
呼吸器リハビリは、慢性呼吸器疾患や肺炎、術後など、
多くの患者さんの生活の質(QOL)に直結する重要な治療です。
しかし現場では、呼吸リハの必要性が理解されている一方で
「十分に提供できていない」という課題も強く感じています。
この記事では、
3学会合同呼吸療法認定士としての経験 をもとに、
呼吸リハの本質・現場の課題・今後必要な改善についてお話しします。
■ 呼吸器リハビリとは?
― 呼吸を“取り戻す”ための包括的アプローチ
呼吸リハは、単に肺を鍛えるものではありません。
呼吸リハの要素は多岐にわたり、
- 呼吸筋トレーニング
- 呼吸パターンの改善(腹式・口すぼめ呼吸など)
- 排痰法の指導
- 運動耐容能の向上
- 姿勢・体位調整
- 不安軽減・心理サポート
これらを統合して、
「息苦しさの軽減」「再入院予防」「活動量の向上」 を目指します。
▼ 科学的根拠(エビデンス)
- COPDに対する呼吸リハは「運動耐容能の改善」「息切れの軽減」「QOL改善」に強い効果あり
(日本呼吸器学会 COPDガイドライン 2023) - 急性増悪後の早期リハビリで再入院率が低下
(Pulmonary Rehabilitation after COPD Exacerbation: Cochrane Review 2016)
エビデンスは豊富で、
呼吸リハは世界的に「標準治療」と位置づけられています。
■ 現場で実感する呼吸リハの価値
呼吸器疾患の患者さんの多くは、
“息苦しさ”が身体・心の両方を大きく蝕んでいます。
痛みよりも苦痛度が高く、
恐怖や不安を感じやすい症状です。
そんな中で、僕たちが最初に行うのは
「今できること」を一緒に見つけること。
- 椅子に座る
- 座位で呼吸練習をする
- 短時間の移動を試す
- 排痰を促す姿勢をとる
小さな改善でも、
患者さんの表情が変わる瞬間があります。
“努力すれば変われる”という希望を取り戻す
これが呼吸リハの最も大きな価値だと感じています。
■ 現場で直面する3つの課題
医療現場では、呼吸リハの重要性を理解しながらも、
次の課題が大きく立ちはだかります。
① 時間と人員が足りない
急性期病院は在院日数が短く、
十分な介入回数を確保できないことが多い。
- 1日数回の介入が本来望ましい
- しかし実際は1回が限界の場面もある
- 看護業務との連携が追いつかない
早期離床・廃用予防が重要と分かっていても、
制度と現場のギャップが大きい。
② 専門知識を持つスタッフの偏在
呼吸器リハは専門性が高い分野ですが、
- 呼吸評価
- 呼吸筋・補助筋の理解
- 体位ドレナージ
- 在宅酸素・NPPVの知識
これらを体系的に学んだスタッフはまだ少数です。
「詳しい人がその病棟にいるかどうか」
で介入の質が大きく変わる現状があります。
③ 在宅との橋渡しが弱い
退院しても呼吸リハを継続できない地域も多く、
再入院の一因になっています。
- 在宅リハの知識不足
- 呼吸リハ継続施設の不足
- 情報共有の不足
在宅でセルフケアを継続できるかどうかは、
退院後の生活を大きく左右します。
■ 課題を乗り越えるために必要なこと
僕が認定士の立場から感じる改善策は次の通りです。
① 早期介入と多職種連携の徹底
- 医師
- 看護師
- リハスタッフ
- 呼吸療法認定士
- 栄養士
これらが入院初期から情報共有できる体制をつくることが重要です。
② 退院前指導の標準化
患者さん・家族への教育が不十分だと、
在宅で急速に機能低下してしまいます。
必須項目:
- 呼吸法(腹式・口すぼめ)
- 排痰法
- 体位管理
- 家でできる運動
- 再増悪の兆候
- HOT・NPPVの管理
③ 地域連携の強化
在宅医療スタッフへ
- 呼吸目標
- リスク管理
- 排痰方法
- 運動プラン
を共有するだけで、再入院を防ぐ力が大きく変わります。
■ 認定士としての想い
3学会合同呼吸療法認定士の資格を取ったことで、
「呼吸」を多角的に捉えられるようになり、
患者さんの変化をより深く理解できるようになりました。
そして今感じているのは、
呼吸リハは“命の質を守る医療”である
ということです。
時間がない現場でも、
専門家が少ない病棟でも、
できることは必ずあります。
これからも、呼吸リハの価値を広め、
患者さんが「少しでも楽に過ごせる時間」を増やせるよう
僕は学び続けたいと思っています。
■ まとめ
- 呼吸リハは科学的にも効果が証明された“標準治療”
- 現場では時間・人員・専門知識の不足が大きな課題
- 在宅との連携不足は再入院につながりやすい
- 認定士として、現場と地域をつなぐ視点が求められる
- 患者さんの「息苦しさ」を軽減することが最大の価値
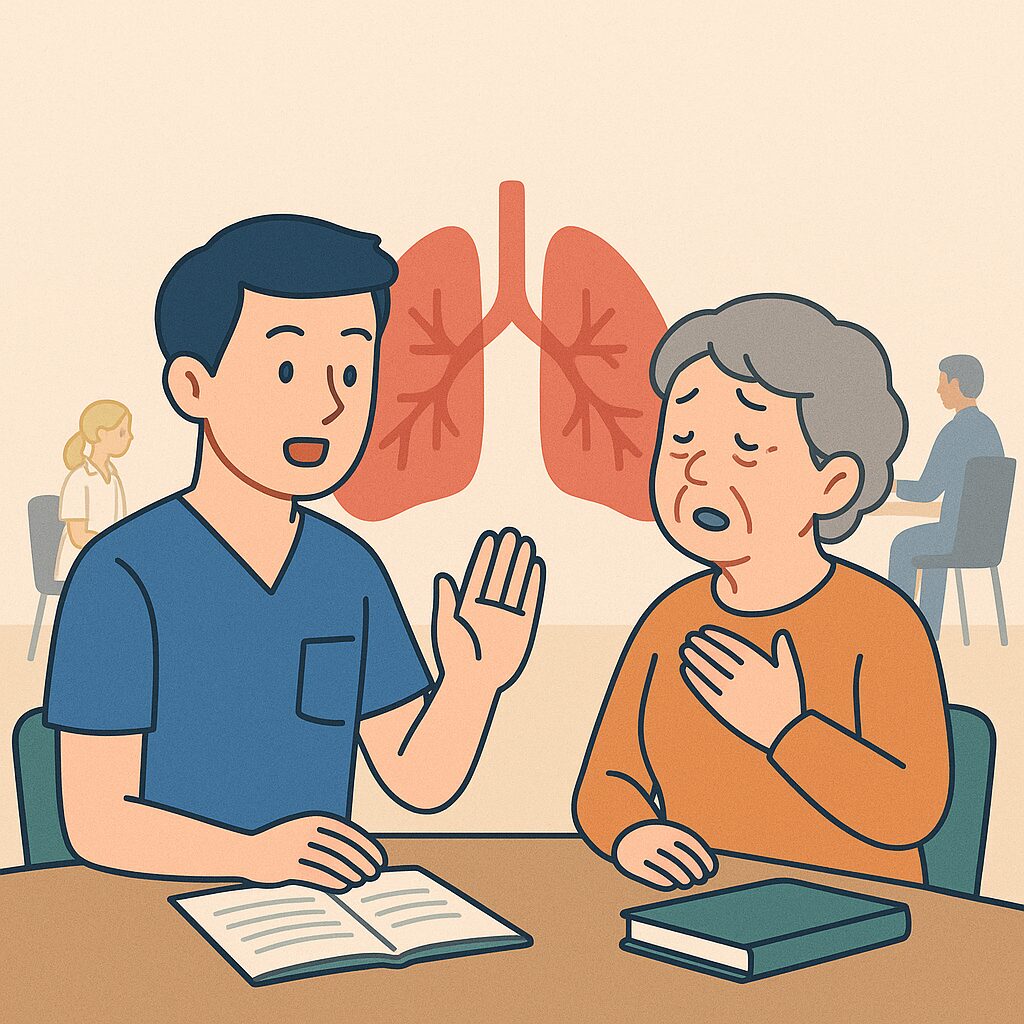


コメント