はじめに
理学療法士になって初めて担当した心不全患者さんとの出会いは、僕の臨床人生を大きく変えました。
あのときの経験が、いま僕が「心臓リハビリテーション指導士」や「3学会合同呼吸療法認定士」として活動する原点になっています。
この記事では、
- 1年目で直面した“心不全リハビリの怖さ”
- 後悔を力に変えた学びの道
- 若手理学療法士や、患者さん・ご家族へのメッセージ
をお伝えします。
臨床1年目、心不全の“怖さ”に直面した日
初めて循環器疾患を担当したのは、心不全を患う高齢の女性でした。
当時の僕は「リハビリ=運動すれば良くなる」という固定観念にとらわれ、息苦しさを訴える彼女に積極的に運動を進めてしまいました。
訓練中、彼女は強い息切れを訴え、足先は紫色に変化。僕自身も「怖い」と感じる場面が多くありました。
しかし、その原因を理解できるほどの知識は、当時の僕にはありませんでした。
急性増悪と別れ――残された後悔
数日後、彼女は心不全の急性増悪で亡くなりました。
「もっと知識があれば…」
「無理に運動をさせず、寄り添っていれば…」
強い後悔が心に残り、それは今でも消えることはありません。
後悔を力に変える ― 資格取得への道
この経験をきっかけに、僕は心不全や呼吸器疾患について深く学ぶ決意をしました。
そして「心臓リハビリテーション指導士」や「3学会合同呼吸療法認定士」という資格取得に挑戦。
病態生理、運動処方、薬物療法、多職種連携など幅広い知識を身につけ、「二度と知識不足で後悔したくない」という思いを力に変えました。
現場で学んだ“知識”と“寄り添う姿勢”
資格で知識を得ても、臨床の現場では患者さんにリハビリを断られることもあります。
「息が苦しいのに運動なんてできない」
「なんで苦しい思いをしなきゃいけないのか」
その声から学んだのは――
“正しさ”だけでは患者さんからの信頼は得られない ということでした。
患者さんの声に耳を傾け、病態を観察し、一緒に目標に向かう姿勢こそが信頼につながるのだと実感しました。
💬 若手理学療法士へのメッセージ
臨床で「怖い」と感じることは、決して悪いことではありません。
それは「このままではいけないのでは?」と気づけている証拠だからです。
不安や後悔を感じたら、それを次につなげてください。
その積み重ねが、次の患者さんを守る力になります。
🕊 患者さんとご家族へのメッセージ
心不全と診断されると、不安や恐怖でいっぱいになると思います。
「どう声をかければいいのか」と悩むご家族も少なくありません。
でも、人は一人で病気と向き合うよりも、誰かと一緒に過ごすことで活力を得られます。
ときには病気のことを忘れて、安心できる時間を持つことも大切です。
知ることは怖さを伴いますが、同時に選択肢を増やしてくれるものでもあります。
僕の発信が、少しでもその力になれれば嬉しいです。
まとめ
心不全患者さんとの出会いと別れは、僕の原点です。
その経験があったからこそ、学び続ける姿勢と、患者さんに寄り添う気持ちを持ち続けられています。
- 若手療法士の方へ:怖さや後悔は、成長の糧になる
- 患者さん・ご家族へ:寄り添い合うことが病気と向き合う力になる
経験は誰かの力になります。
これからも理学療法士として、少しでも皆さんの助けになれるよう学び続けていきます。
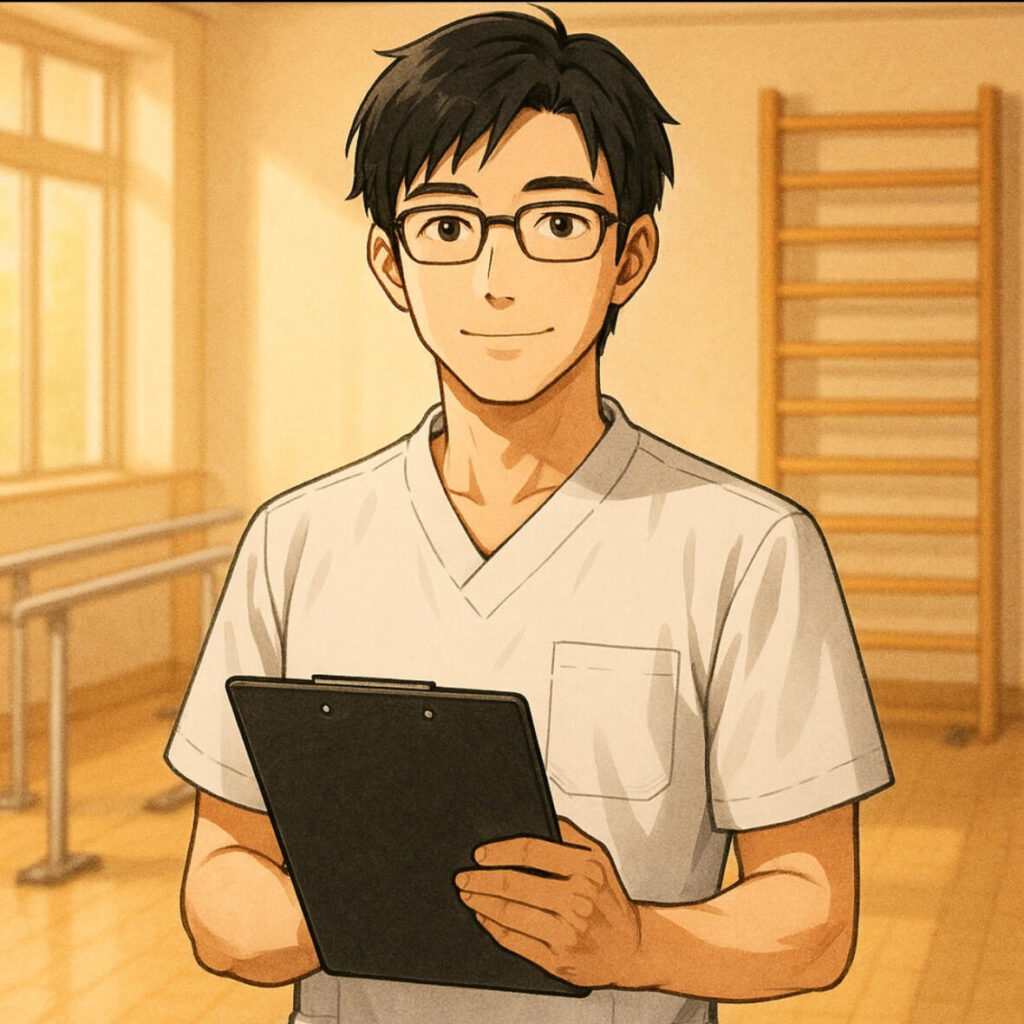

コメント